このコンテンツは獣医療従事者向けの内容です。
掲載記事は掲載日時点の情報であり、記事の内容などは最新の情報とは異なる場合があります。
はじめに
猫の炎症マーカーとしてのSAA(Serum Amyloid A)に、皆さんはどのような印象をお持ちでしょうか? 本コラムでは長らく猫のSAA研究に携わってきた著者が、その有用性や使用感について率直なところを述べていきたいと思っています。
ただし、本コラムの内容はあくまでも著者の個人的な経験や観測に基づく意見であり、学術的に正しいとは限らないことにご留意ください。また、このコラムについては社としての見解ではなく、あくまでも個人的な意見となっております。
SAAがすごく高いってどのくらい?
猫SAAを測定すると、病気によっては200μg/mL以上といった高値が得られることがしばしばあります。犬のCRPの感覚で数値だけを見てしまうと、ギョッとするかもしれません。しかし、これには数字のトリックが潜んでいます。猫SAAの単位はμg/mLであり、犬CRPの単位はmg/dLです。これについては慣例的なものなので理由も何もないのですが、単位が違うんですね。100mL = 1dLであり、1000μg = 1mgですので、猫SAAの測定値を10で割ると単位をmg/dLにそろえることができます。そして私の感覚としては、単位さえそろえてしまえばCRPとSAAの程度は同じくらいかなと思っています。
例えば、犬でCRPが2~3mg/dLくらいだと、ちょっと高いなぁという印象を持ちます。これが猫のSAAだと、20~30μg/mLくらいに相当するわけです。CRPが5mg/dLを超えると明らかに高いと感じますが、これが猫SAAだと50μg/mL以上ということになります。冒頭の猫SAAで200μg/mL以上という数値は、犬CRPだと20mg/dL以上ですから、ほぼ測定上限ですね。重篤な状態ではありますが、全く見ないというほどでもありません。十分あり得る数値です。もちろん犬と猫の違いはあるはずですし、そもそも炎症マーカーの数値の大きさは必ずしも炎症の程度を反映しませんが、感覚としてはこれでそれほど外れていないと思います。
SAA測定値のイメージの掴み方

猫SAAは犬CRPと同等なのか?
おそらく、セミナー等でいただいた質問の中で一番多かったのがこれだと思います。
日本では犬の炎症マーカーとしてのCRPが広く普及しています。まれに不思議な挙動をとることはありますが、大部分の症例ではCRPは概ね「予想通り」に変動します。発熱や明らかな炎症部位があり、上がってるだろうなというときはちゃんと高値になるし、治療がうまくいったらちゃんと下がります。そのため、CRPを指標に治療計画をたてたり、退院のタイミングを図ることが可能です。不明熱のような、よくわからないけどなんとなく調子が悪いという症例で測定すると高値になっているので、それをきっかけに検査を進めることができます。このように、CRPはわりとわかりやすいマーカーであり、そのことも普及を後押しする一因になったことでしょう。
猫SAAが院内で測定できるようになった時、多くの獣医師が犬のCRPを使うような感覚で使おうとしたことだろうと思います。そして、その結果として何か違うと感じたのではないでしょうか? 私も、両者はやはり少し違うと感じています。しかし、その違いを一言で言い表すのはなかなか難しい……。
猫が変なのかSAAが変なのか
CRPもSAAも、ともにMajorな急性相タンパク質に分類され、その炎症時の挙動は類似しているとされています。しかし、人でCRPとSAAを同時測定すると、その一致率は8割程度ともいわれており、ぴったり一致するわけではありません。そのため、CRPのイメージでSAAの値を予測しようとするとブレが生じるのではないか、というのが一つの仮説です。ただし、人ではCRPとSAAの不一致ではSAAは高値だがCRPは基準範囲内という例が多く、その要因としてウイルス感染などが挙げられています。ウイルス感染ではSAAは上昇するものの、CRPは上昇しないため、それが違いを生んでいるというわけです。しかし、この理屈だとウイルス感染の比較的多い猫ではSAAはより高値例が多いのでは?と思いますので、なんとなく猫には当てはまらない気がします。
SAAというタンパク質はHDL分画に結合して存在するという特徴があり、脂質代謝と密接な関係があります。人と猫では脂質代謝が異なりますので、その結果として測定されるSAAの値にも違いが出ているという可能性はあると思われます。ただし、脂質とSAAの関係、そして猫の脂質代謝について十分なデータがあるわけではなく、どのような影響が出るのか、どのような違いが生まれるのかは明らかではありません。
犬と猫の違いというのも見逃せない要因です。最近よく言われるようになりましたが、猫は小さな犬ではありません。単純な細菌感染などならともかく、同じ病名であっても犬の急性膵炎と猫の急性膵炎、犬のリンパ腫と猫のリンパ腫は全く同一というわけではなく、異なる特徴を示します。誤解を恐れずに言うなら、猫は変な生き物です。診察をしていて、犬と猫のどちらが難しいかと聞かれれば、私は迷わず猫と答えます。猫の研究をしてきた分それなりに猫の患者さんを診察してきましたが、やはり犬のほうが圧倒的にわかりやすいし、対処しやすいと感じます。SAAが変なのではなく、猫だから。そんな仮説は、乱暴すぎるでしょうか……。
猫だからなのか、SAAだからなのか、はたまた猫のSAAだからなのか。現状では、この疑問に対する答えは出せませんが、とりあえず犬のCRPとは挙動が異なると考えておいたほうがよさそうです。そして、SAAの挙動の“クセ”を掴むための最良の方法は、とにかく数多く測定し、感覚を身につけることです。

下がるのが早い
実感として、SAAは治療開始後下がるのが早い、ともすれば早期に下がりすぎると感じています。
これにはいくつかの理由が考えられますが、一つは血中半減期の違いでしょう。CRPにしてもSAAにしても、炎症反応に呼応して血中濃度が上昇し、炎症反応が消失すれば産生が抑えられるため、徐々に血中濃度は低下していきます。
しかし、実際の臨床例では治療を始めたからといってある瞬間にピタッと炎症が止まるわけではありません。そのため、正確に血中半減期を求めるのはなかなか困難であり、CRPについての人の報告では、5~47時間とかなり幅があります。SAAについての報告は多くありませんが、CRPよりも短いという記載が見受けられます。
犬や猫についてはさらに報告が少ないため正確なところは定かではありませんが、感覚的に犬のCRPの半減期は24時間かそれより少し短い程度かなと思っています。典型的な免疫介在性多発性関節炎の症例はプレドニゾロンによく反応しますが、そういったケースで診断時20mg/dL以上だったCRPの値が、1週間治療を継続するとだいたい基準範囲内まで下がってきます。そこから逆算すると、半減期はそのあたりかなと。そして、猫のSAAの半減期はそれよりずっと短く、12時間かもっと短いのではと感じています。
もう一つの可能性として、検出感度の問題が考えられます。猫のSAAの測定が世の中に出てきた当初は人の測定系を流用していましたが、そのために低濃度域での検出感度が悪いのではないかということはずっと指摘されていました。
SAAが十分量ある場合は問題ないのですが、SAAが少ない場合には抗体との結合性が低下し、うまく検出できないという現象が生じます。このことが原因で、ある濃度以下まで血中濃度が低下するとすべて基準範囲内として結果が出てしまっていた可能性があります。現在は検出系も改良されており、この問題は解消したと思います。しかし、普段はHDLと結合する形で存在するといったSAAタンパクの特殊性を考えると、特に低濃度の場合には実際よりも低い数値となっている可能性は否定できません。
仮に半減期が12時間だとすると、正しく測定できているとしても200μg/mL以上の高値が3日後には基準範囲内まで下がる可能性があります。しかし、それが症状の改善と必ずしもリンクしていないと、退院や治療変更のタイミングを見誤ることになります。治療がうまくいっているかどうかの判断基準としては問題ないと思いますが、薬の減量や退院のタイミングを決める基準としては、少し慎重になったほうがいいのかもしれません。
高値だと予想したのに上昇していなかった
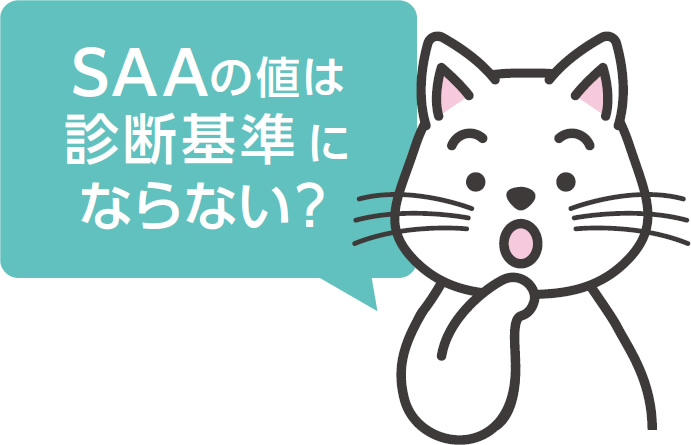
実際に診療していて多いのがこのパターンです。ただ、この話をする前に確認しておかなければならない重要なポイントは、SAAの値は診断基準にはならないということです。診断はあくまでもほかの血液検査や画像検査、細胞診などの結果に基づいて下されるべきものであり、SAAの測定結果によって診断名が左右されるべきではありません。きちんと診断したうえで、今後のモニタリング等に使おうと思ってSAAを測定したら思ったよりも上がっていなかった、そういう状況を想定して書いています。
この理由として、まずは前述したような猫だから、SAAだからということが考えられます。SAAが高値だろうと予想したのは、たいていの場合犬のCRPの経験に基づいています。しかし、犬でもなければCRPでもないので、予想通りにいかないのはある意味で当然なのかもしれません。どういった病態や疾患、どういう状況でSAAが高値になるのかについては少しずつ情報も増えていますが、地道に測定を続けて経験を積み重ねるしか現状では対応策はないかもしれません。
2つ目の理由として、前述した下がるのが早いということとの関連が考えられます。特に私はずっと2次診療に携わってきましたので、診察する猫の患者さんはたいていの場合何らかの治療を受けた状態で来院されていました。十分に奏功していなかったとはいえ、その治療によってSAAの値が下がってしまっていたことはあり得ると思います。実際に、1次診療施設でとられたデータを見ると私の経験とはやや異なる部分があるため、事前の治療の影響や検査のタイミングが影響している可能性は十分に考えられます。転院症例などの場合や、病歴がある程度長い場合には、結果の判断は慎重にするべきかもしれません。
予想外の高値
私個人としてあまり経験はありませんが、健康診断時にCRPやSAAを測定すると思いがけず高値だった、ということがしばしばあるようです。
CRPもSAAも、その産生機序や測定原理を考えると偽陽性はほぼないはずなので、測定エラーさえなければ高値の場合には何らかの異常を疑う必要があります。特に高齢の動物では腫瘍などが隠れている可能性が考えられますので、症状がなくても高値であれば、全身の画像検査(X線検査および超音波検査)と尿検査くらいは実施すべきだろうと思います。
このとき注意すべきことは、一部の非炎症性疾患でも炎症マーカーが上昇する場合があるということです。例えば副腎皮質機能低下症(アジソン病)はどう考えても非炎症性の疾患ですが、炎症マーカーの高値がしばしば認められます。そのため、超音波検査で腹部をスクリーニングする際には、副腎のサイズも忘れずにチェックしておきたいところです。
では、一通り検査しても異常が見つからない場合はどうすればよいでしょうか。
この辺りは獣医師の考え方や飼い主の希望にもよるのでケースバイケースですが、本当に何も症状がなくて、ほかの検査項目にも異常がないのであれば、経過観察も一つだと思います。前に述べた通り、著しい高値であっても原因さえ取り除かれれば1週間もあれば基準範囲内まで低下しますので、1週間後の再検査というのは理にかなった選択だと思います。
診断<モニタリング
SAAに限らずCRPもそうですが、炎症マーカーが診療に役立つポイントは診断時よりもむしろモニタリングだろうと個人的には考えています。診断において炎症マーカーの値は参考にはなりますが、決め手にはなりえません。極端なことを言えば、炎症マーカーを測定しなくてもほとんどの疾患は診断可能です。
一方で治療の効果判定や、再発のモニタリングにおいては炎症マーカーは客観的で非常にわかりやすい指標になりえます。もちろん、症状の改善が最優先なのは言うまでもありませんが、疾患によっては目に見えて症状が改善するまでに時間がかかることもあるため、とりあえず現行の治療方針が合っているかどうかを炎症マーカーを指標に判断するというのは、非常に合理的な使い方です。ただし、治療開始前の数値がどうだったのかがわからなければ治療後との比較はできませんので、モニタリングするためには結局診断時に測定しておくことが必要になります。
腫瘍の診断の場合

私も失敗したことがありますが、状況が複雑化した後で初めて炎症マーカーを測定しても、それが大本の疾患の影響なのか、あるいは二次的・三次的な病態・併発疾患の影響なのかを判断することは困難です。そもそも炎症マーカーが上昇するかどうかは、病気の種類だけではなく個体差などの影響を受けます。だからこそ、病気を発症、診断した時点で一度測定しておくことで、「その個体における、その疾患での基礎値」を知ることが重要になるわけです。
例えば診断時に測定して、高値を予想したにも関わらず基準範囲内という結果が得られたとします。その時には予想が外れたことで腹立たしい気持ちにもなりますが、そこで「この患者さんのこの病気ではSAA(あるいはCRP)は上がらないんだ」と頭を切り替えてください。その後の治療過程でSAAの高値が認められたとすると、多くの場合それは元の病気のせいではなく、何らかの二次的要因が関与しています。もちろん、元の病気の影響が絶対にないとは言い切れませんが、少なくとも先ほどのような考えを頭の中に持っておくことで診察を効率的に進めることができるはずです。
終わりに
ここまでつらつらと、SAAの実際の使用感について述べてきました。総評として、犬のCRPが非常に上がりやすいのに対して、猫のSAAは思ったよりも上がりづらい、というのが現状の結論かなと思います。いろいろなデータを見ても、感染症や典型的な炎症性疾患などのわかりやすい病態では割と素直に高値化するものの、病態が少し複雑になると途端に挙動が予測できなくなります。そして猫は、犬よりも病態が複雑化した状態で来院することが多いように思います。
猫だから&SAAだからのダブルパンチで、犬のCRPと比べると理解しづらい面はありますが、うまく使えばちゃんと役に立てるマーカーです。そして、何度か繰り返していますが、SAAの挙動を理解するためには測定数を増やして、それぞれの獣医師の中で経験を蓄積して感覚として磨き上げていくほかありません。長らく猫のSAAを研究してきた者として、SAAを測定してよかったねという声が増えることを願ってやみません。
記事の執筆担当

玉本 隆司 獣医師、獣医学博士
2002年 東京大学入学
2005年より獣医内科学研究室に所属し、辻本先生、大野先生、松木先生らの薫陶を受ける。
2008年に大学卒業後、埼玉の動物病院で2年間一次診療に従事。
2010年に東京大学大学院農学生命科学研究科に進学。獣医内科学研究室で研究に励む傍ら、附属動物医療センターでの診療にも従事する。
2014年に酪農学園大学伴侶動物内科学IIユニットに助教として赴任。附属動物医療センターでの内科診療を担う。2016年より同講師、2019年より同准教授。2017年より内科診療科長、2020年副センター長。
2021年に大学を退職し、富士フイルムVETシステムズ株式会社に入社。
2024年逝去。生前、多くの功績を残し、業界内外から高く評価される。
大学時代の主要な研究テーマは「炎症マーカーの臨床活用」で、特に猫の炎症マーカーであるSAAの臨床応用や基礎研究を精力的に行った。
診療については「専門性がないのが専門」と言いながら、内科全般をオールラウンドにこなし、その中でも免疫介在性疾患や感染症に強い関心を持っていた。
関連情報
VETEVITA 最新号をお届けします

メールアドレスをご登録いただくと、富士フイルムVETシステムズの広報誌「VETEVITA(ベテビータ)」の最新号の発刊に合わせて定期的にご案内いたします。
- * 獣医療従事者の方に限ります。
こちらもご覧ください/動物医療ライブラリ
ペットオーナーさまへの案内にご利用ください
ペットオーナーさま向けに、犬・猫などの健康情報やペットライフを充実させる情報サイトをオープンしました。ぜひペットオーナーさまへの定期的な健康診断や病気の早期発見の大切さを伝える情報としてご活用ください。このページへのリンクはフリーです。SNSや貴院ホームページからのリンク先としてご利用いただけます。















