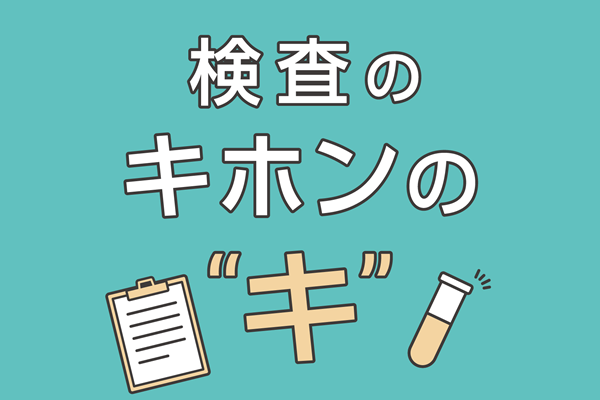このコンテンツは獣医療従事者向けの内容です。
掲載記事は掲載日時点の情報であり、記事の内容などは最新の情報とは異なる場合があります。
臨床検査に関して「感度」という単語が出てくる場合、一般的には特異度の対義語としての感度を指していることと思います。(感度と特異度の本当のトコロ、参照) しかし、検査関連では、もう一つ別の感度が存在します。それが試薬や機器の感度、「検出感度」と呼ばれるものです。
臨床検査では、血液中の物質の量を濃度として捉えるものが大多数です。検出方法は検査項目によってさまざまですが、多くの場合に、検査試薬と目的物質が反応することで発色したり、濁度が変化したりするように設計されています。その発色の程度や濁度の変化を検出器でとらえ、既知濃度のコントロールから設定した標準曲線に当てはめて、濃度に変換して報告するわけです。
標的物質があまりに少ない場合、発色や濁度の変化を検出器でとらえることが出来ません。また、多すぎる場合にも捉えられない場合があります。これが「検出下限」や「検出上限」であり、合わせて「検出限界」と表現されることもあります。試薬や機器の性能の問題で検出できないだけで、たとえ微量であっても理論上その物質の濃度は0(ゼロ)ではないため、「検出限界未満」といった表現がよく使われます。そして、どこまでの精度で検出できるかを指して、検出感度と呼んでいます。
試薬が動物専用に開発されたものであれば、通常はあまり問題になりません。しかし、残念ながら動物専用の試薬は多くはなく、人用に開発されたものを流用しているというのが現状です。検査の中には抗原抗体反応を利用したものもたくさんありますが、抗原抗体反応は種特異性が高いため、人の蛋白質を抗原として作られた抗体が、犬や猫の蛋白質と全く同じように反応するかといえば、そうはいきません。アミノ酸配列や立体構造、糖鎖修飾の違いなどによって抗体の反応性は低下します。
これが全く反応しなければ、検出できない、検査には使えないとなります。使えない場合は残念ではありますが、ある意味で話はシンプルです。問題なのは、中途半端に反応する場合です。その場合には、血中の蛋白質のうちの一部と反応し、それが濃度として測定されます。濃度に変換するための標準曲線は人の蛋白質に基づいて作成されたものですので、そうして出てきた濃度は本来の血中濃度よりは低い値です。この状況を「検出感度が低い」とか「検査の感度が悪い」などと言ったりします。
抗体の反応性が低くても安定していれば、増加や減少などのトレンドをとらえることは出来ますので、臨床検査として利用することは可能です。しかし、検出できる幅が狭かったり、微細な変化をとらえられないなどの問題は生じます。

たとえば血清アミロイドA(SAA)が猫の炎症マーカーとして世の中に出た当時は、人用に開発された試薬を使用していました。その当時の基準範囲は、海外の論文報告に基づいて2.5μg/mL以下とされていることが多かったと思います。当初から猫のSAAについては検出感度がイマイチなことはたびたび指摘されており、特に低濃度域での検出が弱いとされていました。その後臨床応用が進むのに合わせて試薬の開発も進み、現在では猫用に開発された試薬や、猫を含む広い動物種用に開発された試薬が使用されています。そして、その試薬を使用した当社の検査では、基準範囲は5.5μg/mL以下に設定されています。当然ながら、この10年程度の間で猫の体内でのSAA濃度が2倍になったわけではありません。人用の試薬を使っていた時期は、猫のSAAの半分程度しか検出できていなかったわけです。また、試薬が変わってから、10~20μg/mL程度の軽微な増加を見る機会が増えたように思います。これも、従来の人用試薬ではそういった軽度の変動を捉えられていなかったからだろうと思われます。
「検査の感度が低い」という言葉は、二通りの解釈が可能です。病気を検出するための感度(診断感度)の話なのか、検出感度の話なのか……。検査をする側の人間はその検査で目的物質をきちんと測定できているかどうかを気にしますので、感度と言えば検出感度を思い浮かべるでしょう。一方検査を使う側の人間は、それで病気を発見・診断できるかどうかを重要視しますので、感度と言えば診断感度だと考えています。相手がどちらの話をしているのか注意しないと、ボタンを掛け違ってしまうかもしれません。
記事の執筆担当

玉本 隆司 獣医師、獣医学博士
2002年 東京大学入学
2005年より獣医内科学研究室に所属し、辻本先生、大野先生、松木先生らの薫陶を受ける。
2008年に大学卒業後、埼玉の動物病院で2年間一次診療に従事。
2010年に東京大学大学院農学生命科学研究科に進学。獣医内科学研究室で研究に励む傍ら、附属動物医療センターでの診療にも従事する。
2014年に酪農学園大学伴侶動物内科学IIユニットに助教として赴任。附属動物医療センターでの内科診療を担う。2016年より同講師、2019年より同准教授。2017年より内科診療科長、2020年副センター長。
2021年に大学を退職し、富士フイルムVETシステムズ株式会社に入社。
2024年逝去。生前、多くの功績を残し、業界内外から高く評価される。
大学時代の主要な研究テーマは「炎症マーカーの臨床活用」で、特に猫の炎症マーカーであるSAAの臨床応用や基礎研究を精力的に行った。
診療については「専門性がないのが専門」と言いながら、内科全般をオールラウンドにこなし、その中でも免疫介在性疾患や感染症に強い関心を持っていた。
検査のキホンの"キ"コラム(全4回)
VETEVITA 最新号をお届けします

メールアドレスをご登録いただくと、富士フイルムVETシステムズの広報誌「VETEVITA(ベテビータ)」の最新号の発刊に合わせて定期的にご案内いたします。
- * 獣医療従事者の方に限ります。
こちらもご覧ください/動物医療ライブラリ
ペットオーナーさまへの案内にご利用ください
ペットオーナーさま向けに、犬・猫などの健康情報やペットライフを充実させる情報サイトをオープンしました。ぜひペットオーナーさまへの定期的な健康診断や病気の早期発見の大切さを伝える情報としてご活用ください。このページへのリンクはフリーです。SNSや貴院ホームページからのリンク先としてご利用いただけます。