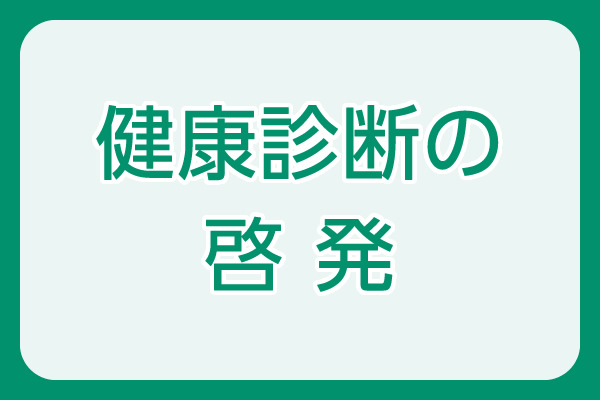このコンテンツは獣医療従事者向けの内容です。
掲載記事は掲載日時点の情報であり、記事の内容などは最新の情報とは異なる場合があります。
新患獲得の手法については「新患獲得のための情報発信ツールの選択」のコラム等でも触れてきましたが、動物飼育頭数がじりじりと減少傾向にある昨今では、高い水準で新患を増やし続けるということは容易ではありません。だからこそ既存の飼主さまに選んでいただける病院づくりを心掛けることが大切です。今回は既存の飼主さまとの関係をより深めるための情報発信のポイントについて紹介します。
マーケティングの分野では顧客のステージや成熟度を分けてアプローチを検討することがありますが、このコラムでも飼主さまの段階を3つに分けて考えてみたいと思います。
1. 来院初期の飼主さまに対する情報発信
特に獣医療のような専門性の高い分野では、病院を運営している側と利用者(飼主さま)の間の情報量の差が大きくなりがちです(情報の非対称性といいます)。こちらが当たり前と思っていることを飼主さまは知らなかったということも少なくなく、長年通院している飼主さまですら「手術ってここでできるんですか!?」「トリミングやっていたんですか!?」という方もいらっしゃるほどです。まずは病院の基礎情報をしっかりと伝えることが大切です。
最も基本的なこととして、診察日、診察時間、予約の仕方、提供している医療やサービスの内容などが一通りわかるような病院パンフレットを1つ作っておき、初診の方に漏れなくお渡しするようにすれば、基本的な情報を飼主さまに伝えやすくなります。さらに、特に力を入れている分野などについては、資料1のようにそれについてまとめた資料を作成し、病院パンフレットと一緒にお渡ししたりDMに同封したりすることで、病院の強みやスタンスについての理解をより深めていただくことができます。病院についての資料が増えてきたら、一式を薄いポケットファイルなどにまとめてお渡しすれば、自宅での保管もしやすく検査結果やワクチン接種証明なども合わせて保管することができますので、喜んでいただけることが多いです。
またLINEや予約システムなどへの登録を最もしていただきやすいのも来院初期です。病院でそのようなツールを運用している場合は来院初期に積極的に告知して、登録を促すようにしましょう。

資料1 病院の取り組みを紹介する資料の例(一部抜粋)
2. 定期的に通院している飼主さまへの情報発信
定期的に通院をしている「かかりつけ」「ファン」といった位置づけの飼主さまの多くは「先生やスタッフさんの話をもっと聞きたい」「病院との距離をもっと縮めたい」という気持ちがあり、病院からの積極的な情報発信を求めている(喜んでくれる)傾向があります。
こういった層の飼主さまは、動物を飼うこと、動物のために何かしてあげること自体に熱心ですので、健康診断のDMなどに反応してくださる方も多いですし、ブログやインスタ、LINEなどでの情報発信を特に熱心に読んで下さる傾向があります。健康についての情報、フードやサプリについての情報などはもちろんのこと、例えば供血犬の募集やトリミングにキャンセルが出ましたというような情報発信にも積極的に反応してくださることが多いです。
またさらに飼主さまとの距離を縮めるために、飼主さまを病院に招いてのイベントや、オンラインのセミナーなどを開催することもお勧めです。当社のクライアントの動物病院でも、歯科セミナー、パピークラス、シニア向けセミナー、子猫のためのセミナー、専門医を招いての飼主さま向け講座、保護団体と協力しての譲渡会など、様々なイベントを開催しています。時間と労力はかかりますが、自院にできる範囲で飼主さまとの距離を縮めるための取り組みを検討してみましょう。

資料2 歯科教室の告知資料の例(一部抜粋)
3. しばらく病院を離れている飼主さまへの情報発信
大前提として、多くの飼主さまと動物にとって動物病院は、「できれば行きたくない場所」であることを理解しなければなりません。昨今は予防や健康診断が普及し、かつてに比べると定期的に通院される飼主さまも増えましたが、それでも動物の体調に異変が無いので数年間動物病院に行っていない、という方も珍しくありません。そのような飼主さまにはどのように対処するべきか、というご相談もよくお受けします。
元も子もない言い方をしてしまえば、意志を持って動物病院に来ていない方はこちらがどのように呼びかけても来院されないことも少なくありませんし、既に転居されたり動物が亡くなったりしているケースもありますので、数年以上来院されていない飼主さまへの情報発信に経済的コスト、時間的コストをかけ過ぎるのは経営の観点から見ると決して得策ではありません。ただ、一部には病院に行くきっかけを逸しているだけの飼主さまもいらっしゃるので、新しい取り組みを開始した際などは、あえて長年来院されていない飼主さまも含めて広くDMなどで周知をしてみるというのもよいかと思います。例えば、猫向けの健康診断を始めた際に猫の飼主さま全員にDMを送ったところ、数年間来院されていなかった方が久々に来院されたというケースは珍しくありません。
また最も大切なのは、そもそも「しばらく病院を離れている」という状況を作らないようにすることです。「1」で述べたように、来院初期の頃から積極的に情報発信をし、飼主さまとの関係性を構築していくことが重要です。

【2025年1月/文責:動物病院経営パートナーEn-Jin 代表取締役 古屋敷 純】
VETEVITA 最新号をお届けします

メールアドレスをご登録いただくと、富士フイルムVETシステムズの広報誌「VETEVITA(ベテビータ)」の最新号の発刊に合わせて定期的にご案内いたします。
- * 獣医療従事者の方に限ります。
こちらもご覧ください/動物医療ライブラリ
ペットオーナーさまへの案内にご利用ください
ペットオーナーさま向けに、犬・猫などの健康情報やペットライフを充実させる情報サイトをオープンしました。ぜひペットオーナーさまへの定期的な健康診断や病気の早期発見の大切さを伝える情報としてご活用ください。このページへのリンクはフリーです。SNSや貴院ホームページからのリンク先としてご利用いただけます。